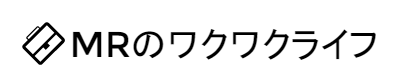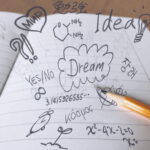こんにちは、複業MRのなすたかです。
ぼくはこのサイトやブログで書評を書くことがあるのですが、ふと「なぜ書評を書いてるのか?」と考えることがありました…
ということで、改めて書評を書く理由をまとめてみました。
複業MRとして書評を書く理由
結論から言うと…
参考になる考え方を自分のものにするため。
ですが、なんで書評を書くようにったというところから振り返ってみました。
大きな転機となったのがある自己啓発本です。
その本をきっかけに勉強に対する意識ががらっと変わりました。ぼくのなかのパラダイムシフト体験ともいえます。
それは「1日30分」を続けなさい!/古市幸雄」という本。
なぜこの本を買ったのか今では覚えていませんが、本を読んだ衝撃は覚えてます。
この本をきっかけに「勉強=試験のため」だった頭が切り替わり、「勉強=自己投資」にシフトしていきました。
そして、自己啓発本を読み漁るようになりましたが、なかなか本の内容が活かせない…読んで満足してしまう。という状態に陥るように…
そこで、読書を活かすための本を読んだりして、読書メモをはじめました。
これがぼくのなかの書評の原型です。
インプットする目的として読書メモなどをいろいろ試してみました。
当時は、ブログやウェブサイトなどをやってなかったので、ノートに参考になる文を写し、自分のなかに落とし込むようにしてました。
スマホも普及してなかったので、ノートが必需品で、こだわってモレスキンを使い続けてました。最近ではノートを持ち運ぶことも少なくなりましたが…
その読書メモがアナログ(ノート)から、今では、ブログやウェブサイトというデジタルに変わってきました。
さらに、他の人にも読んでもらうことも意識するようになり、ノートに書いていた頃より、内容もよりわかりやすく正確になっていきました。
ノートの場合、「自分しか見ない」+「手書き」なので、正確さというよりは、ニュアンスが伝わるように書いていましたが、不特定多数が見る可能性のあるブログやウェブサイトでは、引用などを正確にすることなどの違いがあります。
これが現在の書評のスタイルになっています。
元を辿れば、自分だけのノートだったものですが、今では公開してインターネット上に残しておくことで、簡単に自分の思考を辿ることもできるようになりました。
書評は書くことが目的ではなく、書いて活かすことが目的
書評を書く理由を考えてみたところ、参考になる考え方を自分のものにするため。
という結論になりましたが、実はある記事を見て、本を読む意味、目的を改めて考えるようになり、この記事を書いています。
そのきっかけとなった記事がこちら▼
キングコング西野さんのブログなんですが、この記事にこんな言葉が…
絵描きのライバルは絵描きではなくて、可処分時間を取り合っている全てのエンタメだから。
これをみて、ある本を思い出し、書評を書く理由はこれだ!と気付きました。
ある本とはこちら▼
この本に西野さんの記事にあったような考え方が…
東京ディズニーリゾートよりも私が脅威に感じている競合の1つに「スマートフォン」があります。テーマパークにとっては、「非日常への現実逃避」、「時間を取り合う」、「可処分所得を取り合う」などの意味において、同じ土俵で争っている恐るべき競合です 。
予想ですが、西野さんもこの本を読んで咀嚼して、自分のものにしたんじゃないかな?と。
この流れを見て、書評を書く理由、(というか本を読む理由ですが)は、
本の内容を腹落ちさせて自分のものにする。
自然と自分の考えにできるようにすること。
だと気付きました。
キンコン西野さんすごい…