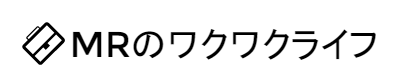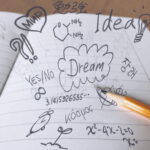こんちには、複業MRのなすたかです。
現在、勉強中の不動産投資についての書籍レビューです。
本のタイトルは「ほったらかし不動産投資で月50万円稼ぐ!/午堂登紀雄」
数年前に不動産投資を行おうと意気込んでいたときに購入したので発行は2011年。6年の書籍ですが、不動産投資に対する基本姿勢から具体的な流れノウハウなど参考になるものばかり…これから不動産投資を始めたいという方にはもってこいの内容です。不動産投資って難しいんじゃない?と思ってる方は是非読んでみてください!
内容を自分のものにして、不動産投資を実践するためも紹介していきます。
▼2018年7月31日追記
この記事で紹介している本は、数年前の本ですが参考になる点がたくさんありました。
そしてMR(サラリーマン)として不動産投資を実施するなら「ほったらかし」がポイントだというのは今(2018年)も変わらないことだと思います。
それを実践できるサービスを見つけました!実際にそれを使って不動産投資をはじめる予定です!
関連記事 「Renosy(リノシー)」の口コミ・評判など!資料請求をした結果…MR(サラリーマン)におすすめの不動産投資だと判明!
不動産投資の難しさ「不動産投資は人生の柱にはならない?」
冒頭から期待を裏切るようですが、見出し通りです。
「不動産投資は人生の柱にはならない」という考え方が基本となっているので、不動産投資によってアーリーリタイアを考えている方は、参考にならないかもしれません。
では、どんな人を対象としているのかというと…
本書は、リタイアしてのんびり過ごしたい人ではなく、ほったらかし不動産投資によって「好きなことを仕事にする」「仕事を通じて成長する」という夢を持った人に贈ります。
あくまでもメインではなく、いかにほったらかしにして「自分のやりたいこと」に集中できるかに特化した不動産投資の本です。不動産投資をライスワークとして回し、自分はライフワークに時間が割くというのが理想。
2011年当時もここに共感して購入したのだと思います。今(2017年)は、ぼく自身も特にこのスタンスを明確にしていて、アーリーリタイアではなく、収入の複線化、ベーシックインカム的な位置づけで不動産投資をとらえています。(別に仕事を辞めて大家さんになりたいわけじゃない)
そのため、久しぶりに読んだ本でしたが、著者のスタンスに冒頭で共感。内容にも非常に参考になりました。
この他にも考え方として…
「年齢・性別・職業に関わらずどんな立場の人であれ、働かなくても得られる「安定的な副収入源」をもつべき
との一文も、「安定的な副収入源」というと、最近、話題になっているベーシックインカム的な考え方ですね。その主張の背景として、考え方や行動に自由度が増すとのこと。
別の本を読んだ時も同じことが書いてありました。
参考記事「MRで消耗したら農家という選択肢もあり!?脱サラ農業について」
こちらの記事では「第2の井戸」という表現で、「第2の井戸」=本業以外の収入を作ろうという内容でした。
不労所得によって得られるメリットは、早期リタイアなどではありません。それは「好きなことを好きな時間に好きな人と好きなスタイルでやる」ための地盤づくりができるということ。
▲この地盤をつくるための手段の一つとして不動産投資を捉えていればいいですね。不動産投資ばかりに頭がいってしまっては元も子もないので注意が必要。
投資とは、極論すれば金儲けの手段にしか過ぎません。専業投資家でもない限り、投資は人生の柱にはなり得ない。
著者はこう言い切っています。
その理由として、投資では仕事で味わえるような成長はが感じらず、仕事を通じて成長できる、ということでした。
そういった考え方から、この本に関しては、不動産投資をいかにほったらかしにしながら稼ぐことができるか、という視点で書かれています。
投資には時間も労力もかけず、ラクして稼ぎたい。こんな思いからたどり着いた方法が、
1、都心・駅近の物件を買う
2、優秀なパートナーとチームを組む
という不動産投資のやり方
特にMRには魅力的。なかなか不動産投資ばかりに時間を使っていられない、むしろその時間は最小限に抑えたいと思っているビジネスパーソンには最適ではないでしょうか。
不動産投資は難しい?区分所有と一棟マンションとは?
不動産投資といってもマンションをまるまる一棟購入するだけではありません。マンションの一室を購入して運用するのも不動産投資の一つです。これは区分所有などと言われています。
そして区分所有とマンション一棟を購入するのでは、意味合いがまったく異なってきます。
不動産投資における区分所有・区分マンションの特徴
本書による区分マンションの特徴は…
区分マンションは、一棟と比べて手間がかからないことです。通常は区分所有者による管理組合があり、躯体(建物の構造や共用部分、外装)の修繕計画が立てられますから、自分で管理する必要がなく、手間がかからないというメリットがあります。
それに、区分マンションは建物の割合が大きいため、減価償却費という経費を多く計上出来ます。これが所得の圧縮に貢献してくれる。また一棟物件と比べて金額も安いですから売却も容易
手間がかからない、金額が安く、売却が容易というのが区分マンションの特徴。
一方、一棟マンションの特徴は…
一棟物件は、外装の修繕などは自分で判断しなければならいですし、節税効果が、小さく、売却にも時間がかかります。その代わり、土地が残りますし、何より収益性が高い、という特徴がある
売却に時間がかかる、収益性が高い、また自分の判断が必要なので、ある程度経験がないと判断できなそう。
以上が区分マンションと一棟マンションの特徴。
これを見ると初心者には区分マンションのほうがよさそうです。その後に一棟マンションに挑戦って流れでしょうか。
不動産投資で選ぶのは新築か中古か?
不動産も車と同じで新築物件は買ったらすぐに値下がりします。
そのため「割高な新築物件を避け、中古物件を中心に選べ」と一般的に言われていて、実際ぼくも中古のほうがいいのかなと思っていました。
ただ、区分所有と一棟買いではこの考え方も異なるとのこと。一棟買いでは、新築でもそこまで割高になることは少ないようです。
その理由を引用して紹介します。
新築の投資用ワンルームマンションの場合は、20戸あれば20人の購入者を見つけなければなりませんから、それなりに手間と費用がかかります。
売る側のことを考えればごくごく自然のことで、例えば、20戸のマンションで一室ずつ合計20人の購入者を見つけるためには、パンフレットの作成や、営業マンを雇う、新聞広告、モデルルームの設置など、さまざまな方法でアピールしなければなりません。
当然、マンションのディベロッパーや、販売会社はこれらの費用を回収するするために、マンション価格に上乗せする…新築マンションが割高になる…
これが新築のマンションが割高と言われるゆえんです。
ただし、投資用の一棟物件になると、少し話は違うとのこと。その理由は、「一棟物件だと売るためのコストがほとんどかからないから」です。
なぜコストがかからないのかというと、一棟だと広告や営業マンに頼らずともいい物件であればFAXや電話ですぐに購入者が見つかるためです。
新築一棟の売り主は、自社の顧客や知り合いの不動産会社へ、図面のFAXを流すか、メールを送るだけです。よい物件であればすぐに買い手が見つかります。
営業マンもチラシ広告もモデルルームも必要なし。確かに業者の利益は乗っていますが、過大な利益を乗せなくても、そこそこ儲けが出ます。
しかも新築一棟の売り主は建売業者やディベロッパーであり、建てて売ってナンボの世界です。だから物件を回転させなければなりせん。
銀行から資金を借りて建てているケースも多く、手持ちの物件が売れなければ次の借り入れができませんから、販売に苦労するような無茶な値付けはしないものです。
つまり、そこそこの利回りがとれる物件が供給されやすいと言えます。
ですから、一棟物件は新築であっても、ワンルームマンションのように、無理に割高になることはないのです。
さらに貸し付けのことを考えると「中古よりは新築が好まれる傾向がある」、設備に関しても「初めはメーカー保証がついているため、しばらくは修繕費がかからない」、「ローンもその物件の耐用年数フルで組める」など、新築ならではのメリットもあるので、一概に新築だからダメということではないとのことでした。
どちらがいい悪いではなく、客観的に判断する必要があるわけですね。
不動産投資は難しい?→ほったらかしで経営すれば難しくない!
冒頭にもありましたが、この本のスタンスはいかにほったらかしにしてラクに稼ぐことができるか?ということです。
その具体的なステップがこちら…
ほったらかし大家さんになるためのステップ
- お金を貯める
- 勉強する
- ほったらかし不動産チームを作る
- 不動産業者にアポイントのメールを送る
- 不動産業者を訪問する
- 質問して相手を見極める
- 物件を購入する
- 信頼できる管理会社に任せる
- ほったらかし管理のための仕組みをつくる
こちらが、不動産投資におけるほったらかし経営のためのざっとした流れになります。
勉強の部分では、書籍やセミナーなどで他人の成功談を聞くなどして、参考にしながら自分に落とし込んでいくことが重要です。
人によって投資のスタンスがことなるため、それをしっかりと見極めて情報を取捨選択するフィルターをもっておくと良さそう。
ぼくは今(2017年9月)、この段階。不動産投資に関するいろんな書籍を読み漁り、知識を習得中。
不動産投資は数千万円、数億円の規模になりますから、物件選びを間違うと、致命的です。そのため、ゲームのルールを知る、つまり、不動産投資の仕組みとリスク、リスク回避の方法を知っておくのは、とても重要です。
かといって、すべてを知らなければ始められないわけではありません。
この考え方は重要ですね。勉強し始めるとあれもこれもとなりがち。
そうではなく、ポイントを抑えておくことが重要。すべてを理解するのではなく、不動産投資をして利益を上げるために大事な部分をしっかり押さえられていて、自分で判断できるようになることです。
不動産投資は、できるだけシンプルに考えて、「ここを押さえれば儲かる」という本質を知ることが大切です。
その本質とは、入居者がきちんとはいり、入り口(取得)から出口(売却)でを含めて、最終的にお金がいくら手元に残るのかを考えることです。
さらに不動産投資をほったらかしで成功させるには、優秀な不動産業者を味方にすることが近道のようです。
しかし、裏を返せば、不動産業者を選び間違うと、不動産投資も失敗する危険性が高いことを意味しています。
悪い、利益を出せればいいなどという利己的な不動産業者から身を守るために…2つの方法があるとのこと。
一つ目は自分自身が知識・経験の武装をして、物件の良し悪しや価格の妥当性を見分け、空室を埋めるアイディアを出す、いうこと
もう一つは本書のメッセージでもありますが、優秀な不動産業者と悪徳業者を見分ける目を養い、優秀な業者と良い関係を保ってやっていく、という方法
具体的にどんな業者がいいかというと、なんとなく大手がよさそうと考えがちですが、著者いわく大手だからといって安心できるわけではないとのこと。
その理由は、不動産業界は、特に人による能力の差が激しいため。(製薬業界も似てるかな?)
また、大手のメリットとしては、物件情報が多く入ってくるぐらいとのことで、逆にデメリットはいろいろあるようです。
著者の実体験だと、大手と言われる有名企業ほど、ノルマが厳しく、とにかく売らなければという姿勢になりがちとのこと。
さらに人の入れ替わりの激しさから、個人の能力が育っていないケースもあるようです。逆に中小企業のほうが、自分でこなさなければならない仕事量が多いので、個人にノウハウが蓄積されていることもある。
会社でみるより「その人」で選んでいかないと失敗しそうです。
そして、そんな優秀な営業マンを見抜くための質問があるようです。
優秀な営業マンであれば、常に最新情報を持っているだけじゃなく、それに対する自分なりの意見があるということなので、それを確認するための質問として…
「最近の不動産投資の環境はどうですか。融資情勢はどうですか。あるいは、今後どうなりそうでしょうか。」
と聞くとよいとのこと。
この質問をすることで、返ってくる答えは、人それぞれというのは当然ですが、ポイントは、話の中身に納得できる具体的な根拠があるかどうか、話の筋が通っているかどうかを見極めること、です。
優秀な人を見極めるって意味では、MRであれば普段からやっているような気がしました。
MRであれば、同業他社のMRと話すときに、この人は優秀か、どれだけ情報をもっているか、などを自然とやっている、MSさんに対してもそうですし、逆もまた然りです。
逆にいうと、顧客側も不動産の営業マンから見極められている可能性は高いですよね。
そのため、優秀な営業マンを見極める以前に「こいつに話してメリットになるか」ということを営業マンに思ってもらえなければ適当にあしらわれてしまういます。まずは情報を与える価値のある客だと思わせることも大事ですね。
その他にも、紹介してくれた不動産に対して、メリットだけの説明になっていないか?というのもチェックポイントです。
メリットだけでなく、しっかりリスクも説明してくれる営業マンでないと怪しいと考えたほうがよさそう。実際に不動産業者のなかにはその物件のメリットしか言わない人もいるようです。
そんな営業マンではなく、
考えられるリスクと、そのリスクに対処する方法があるかどうかを、きちんと提案してくれることが、重要です。
とのことです。
それもリスクをただ伝えるのではなく、その対処法も提案してくれるなど一歩踏み込んだ情報をくれるかどうかですね。
ほかにも、顧客の背景を考えず、とりあえず紹介するような営業マンは避けたほうがいいとのこと。
「とりあえずいろいろ紹介して、顧客が勝手に決めればいい」という「この指止まれ」のスタンスの人もいる
「自分で物件の良し悪しは判断できるから、物件情報さえもらえればいい」という人ならそれでいいのですが、自信がないうちは、なぜお勧めなのか、その理由を聞くようにしましょう。
不動産投資に対するスタンスの違いで、上記にあるように自分で判断できるような人であればいいのですが、そこを目指していないので、「自分にとって、なぜこの物件がおすすめなのか」をきちんと説明してくれるかがチェックポイント。
そう考えると営業マンと合う合わないの話しにもなってくるかもしれません。
いや優秀な営業マンなら顧客のニーズに合わせるのかな…このあたりのことは今後実際に会ってチェックしたいと思います。
物件の選定はプロに任せてしまえばいいのです。ブロの目で見て、そのフィルターを通った物件の中から、よさそうな物件を選べばいい。その仕組みをつくればいいのです。
たしかに、本業をやってて、不動産投資にそこまで時間を割けないなら、任せるところは任せた方が効率的。
「不動産投資の千三つ」という言葉があるようです。1000件の物件をみて、そのうち10件に申し込みを入れ、ようやく3件が買える、という意味。
そんなに時間ないし、できるだけそこに時間をかけずにやっていきたい、そんな方にこの本は本当におすすめ。
どの物件を選ぶかは、自分自身の目標や投資スタンスと密接にかかわってきますから、業者が勧める理由からも、本当に自分のことを考えてくれている業者かどうかが判断できます。
不動産投資における出口戦略が難しい?
不動産投資は20年、30年スパンの運用になるので、金利や周辺状況がどう変わるかわからない。
わからないことを心配しても意味はないので、今考えられるベターな選択をすべき。そのためには…
物件を買ったあと、何年くらい所有し、最終的には売却するのか、更地にして転売するのか、いったん壊して建て替えるのか、ずっと持ち続けて子供に相続するのか、そのくらいの大まかなイメージは持っておいた方がいいでしょう。
例えば、途中で売却を考えているなら、古すぎる物件は避けるべき、など。
また区分マンションでは古くなれば建て替えもあるので、その前に売却するなどが考えられます。
不動産購入時の諸経費とは?
余談ですが不動産投資で購入の際に諸経費なるものがかかります。それは不動産価格の6〜9%程度を想定してるとよさそうです。ちなみに諸経費の内訳は下記のようになっています。
・不動産の登記に必要な登記費用
・仲介手数料(業者が仲介に入っていれば)
・火災保険料、地震保険料
・金融機関への融資手数料
・固定資産税の日割り計算
・契約時の印紙代
・不動産取得税(購入してから半年後くらいに請求がくる)
キャッシュフローをシミュレーションするにあたっての注意点
不動産を購入する前に収支をシミュレーションする必要がありますが、その際の注意点があります。
業者がつくる収支表の経費項目に、たまに減価償却費が入っている場合があります。減価償却費は現金の支出を伴わない経費であり、キャッシュフローには影響しないので、収支シミュレーションの計算からは除外しておきましょう。
減価償却費は不動産取得税の計算に必要な項目で、税金が発生するかどうかを確認するために使います。
では、収支シミュレーションでチェックすべきポイントは、というと金利、空室率、家賃水準です。
金利は現状の借入金利+2%上昇しても大丈夫なくらいを想定しておくとよく、空室率は都心部では5%であれば問題ないが、ただ高めに設定しておくことに越したことはないので10%前後で計算したほうがよいとのこと。
家賃水準については、こちら▼
物件調査は不動産業者に任せても、家賃の査定だけは自分でもウラを取っておく必要があります。
調べておきたいのは、
1、現状の家賃設定が妥当なのかどうか
2、10年後、あるいは20年後に家賃はどれくらい下がり、収支がどう変化するのか、という2点です。
調べ方は、ヤフー不動産のような不動産ポータルサイトで検索するだけ。
自分が買おうとしている物件と同じような条件(最寄り駅、駅徒歩、築年数、間取り、広さ)で検索すれば、今募集されている物件の家賃相場がわかります。
また上記の条件で築年数のみ変えれば、10年後、20年後の家賃相場もわかる。現地調査も重要とのことで、その際には2つのチェックポイントがある
1、購入予定物件の周辺にある、競合物件の入居状況をチェック
競合のマンションやアパートがあっても、満室で稼働していれば問題ないが、空室が目立つなら注意が必要。また更地が周辺にあれば、今後の開発計画を役所で調べたほうがよさそうです。
2、物件の周辺、あるいは最寄駅にある不動産屋に飛び込んで、話を聞いてみる
話しを聞くことで、どんな人が住んでいて、どこに通勤する人が多いか、物件の家賃相場が適正か、入居は決まりそうか、街の開発予定などの情報を得ることができる、とのこと。特に地元で長くやっていそうなところがよく、情報に偏りがでないように2〜3ヶ所回るとよい。
空室になったときの対策とは?
購入後の話しになってしまいますが、不動産投資の大きなリスクが空室です。それを防ぐためにさまざまな手法がありますが、著者は空室になったときの対策として…
家賃を下げることがもっとも手っ取り早い解決策です。
と述べています。家賃を下げるのは最終手段かなと思っていたので、意外でした。
家賃を下げるのが手っ取り早いのは、最近のマンションやアパートは設備面では大差なく差別化しにくい、という理由のようです。そこにコストや労力を掛けても効果がなかったとなりかねない…
特に内見者のためのスリッパや芳香剤など小手先のテクニックはほとんど効かない。
立地が悪ければそういったところで補強する必要があるかもしれないが、立地さえよければ、少し家賃を下げるだけで、意外と入居者は見つかるとのこと。
小手先のテクニックに時間を掛けていては、ほったらかし経営にならない。
ほったらかし経営をするためにも、優良立地にこだわり、家賃を下げる余力がある物件を選ぶようにしているとのことでした。
不動産投資の利回りが難しい?
不動産投資のとっつきにくさは、利回りなどの聞きなれない言葉のせいじゃないかな、と個人的に思っています。言葉の意味も計算式もよくわからないから、敬遠してしまうのではないかと。
ただ、この本では「不動産投資は利回りが命ではない」と言い切っています。
その理由として利回りにはいろいろな計算法がありますが、購入時の利回りと実際の利回りに乖離が発生することが多いため。
利回り20%の物件を買ったと思っても、5年後には10%も取れていない、というのはよくあることです。
もちろん、利回りは投資判断において重要な指標であることは間違いありません。しかし、実際に物件を所有し、何年も運営すると痛感するのてすが、不動産投資は利回りよりも、「手元に残る金額はいくらで、それがどのくらい続くか」が重要だと痛感します。
ちなみにこんな利回りの計算法があります。
表面利回り(%)=(年間賃貸料÷物件価格)×100
ネット利回り(%)=(年間賃貸料-年間運営経費)÷(物件価格+購入時諸経費)×100
投資利回り(%)=投下資金÷年間キャッシュフロー(キャッシュインフロー-キャッシュアウトフロー)×100
投資利回りが会計用語のROI(リターン オン インベストメント)
投下した資金に対していくら利益が得られるか、という意味。
また前述していますが、購入時の注意点として金利が上がった場合についても想定しておくべきとのこと。不動産投資は変動金利なのでそれも踏まえておくことが重要。
投資ローンは賃貸経営という「事業」に対する融資ですから、住宅ローンとは異なり、一般的には変動金利です(3年固定や5年固定などはあります)。
そもそも、金利が上がったことも想定してから購入するようにしておいて、それでも家賃収入以上に返済額が増えてしまった場合には、借り換えや、繰り上げ返済によって返済額を減らす。考えにくいが、それ以上に金利が上がるようであれば売却するしかない、ようです。
その他にもまだまだ参考になる点があったので、別記事でまとめていきたいと思います。
とりあえず購入までに知っておくべき内容はおおむね網羅できたはず。皆さんのご参考になれば幸いです。
数年前に妻の猛反対で諦めた不動産投資に再チャレンジしている「現役MRがゼロからはじめる不動産投資」の実体験はこちらから⇒現役MRが不動産投資をはじめるために行ったこと